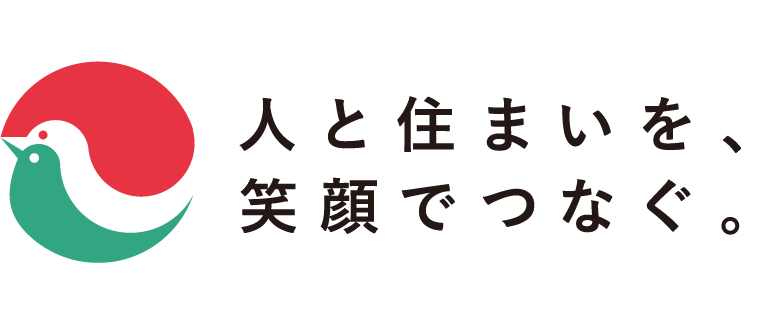千代田区 環境まちづくり部/東京都千代田区
地域を魅力的にする取り組み
<寄稿:2018年2月>
神田発・現代版「家守(やもり)」
によるエリアマネジメント
「家守(やもり)」という言葉を、全国のまちづくりの施策で聞くようになった。家守は江戸時代における地主の代理人で「家主」とも称され、落語に出てくる「大家」でもある。近年、多くの都市の中心市街地がシャッター通りになり、遊休施設の活性化策として、不動産運用とエリアマネジメントの担い手としての家守という役割が再評価され、既存施設を生かす「リノベーションまちづくり」が地域価値を高めるまちづくり手法として注目されている。
「家守」という言葉がまちづくりで初めて使われたのは、2003年3月、(財)千代田区街づくり推進公社※1が実施した「千代田SOHOまちづくり検討委員会(座長・小林重敬)」からの提言書『中小ビル連携による地域産業の活性化と地域コミュニティ再生 遊休施設オーナーのネットワーク化と家守によるSOHOまちづくり施策の展開』※2であった。
本稿では、この提言書の検討経緯から現代版家守の概要と今日的な意味を再確認してみたい。
1.バブル後の神田のまちづくり
私は1997年から8年間、千代田区の外郭団体である「(財)千代田区街づくり推進公社」で、地域に入るようなまちづくりの仕事をしていました。当時はいわゆる「バブル景気」が崩壊した後で、神田では、地上げで放火にあった建物や塩漬けになったままの空き地や空きビルが点在し、夜間人口の減少はもとより、印刷業や繊維業の地域産業構成も大きく変わり、昼間人口も減少している状況でした。そんな中で、地域コミュニティの再生と新たな地域産業の育成に取り組まなくてはなりませんでした。
バブル期に活用された制度の1つに総合設計制度があります。小割された宅地をまとめ、周辺を公開空地にして高層ビルを建て、住民は上層階に住み、低層階を店舗、中間を事務所にすればいいという発想です。しかし、地元の人たちに話をすると「それは違う、人は上に住んだらおしまいだ」と具体的な事例をあげて反論されました。「江戸からの商業地に生活しているのだから、洗濯物に陽があたるのはいいが、商売物にあたったらだめ。公園や路地に緑があるのはいいが、道路上に中途半端な緑はいらない。道路が商売の場だ。コミュニティに入りたければ、地べたで挨拶できなければだめだ」と。
そういえば、神保町の古本屋街や柳原通りの羅紗屋街の店舗は北を向いています。秋葉原に移る前の多町青果市場では、公道を使い相対で取引をしていました。確かに木造密集地で総合設計制度を使うのには有効でしょうが、関東大震災後の区画整理事業で道路率が33%(昭和11年時点)を超える神田のような都心商業地では、単に前面道路を広げる発想だけでは地域は活性化できないことを、地域の方々から教えられました。

図1/2003年頃の千代田区町丁別道路率
図1に見るように、旧神田区の道路率は、駿河台地区を除き大手町丸の内地区と比べても高いのです。関東大震災後の区画整理は3mから44mの多様な道路(公道)を神田につくることで成立しました。同じ道路率でも神田と大手町丸の内とは都市の設計思想が異なりますが、その際、神田のように地権者の多い商業地に対応した都市計画制度がないことに気付かされました。
地域が活性化するために必要なのは、バブルが前提とした法人会社を地域に取り入れることではありません。職住一体であった神田のまちでは、パソコン1つをかついで商売を始めるような個業を行う人材の確保と、その受け皿となるスモールオフィス、ホームオフィス(最近はあまり聞かれなくなった言葉ですが)が必要なのではないかと考えました。そのためには、神田のまちを構成していた棟割長屋ならぬSOHO向けの仕掛けと、それを運営する新しい中小ビルオーナーと連携した不動産賃貸業・管理業が求められていました。
2.江戸・古い公共によるまちづくり
バブル後の低成長期における新しいまちづくり手法を模索する際、明治以降の近代化で失われた、江戸という、低成長時代を支えた「古い公共」のあり方がヒントとなりました。
江戸を指して「八百八町」と、町の数が多いことを特徴のようにいいますが、幕末期にはその倍近い1,600余の町がありました。各町は将軍に対して奉仕する必要があり、国役や公役という役はありましたが、幕府は地主から固定資産税にあたる地子はとりませんでした。町は地域自治の単位として存在し、そこで必要な上下水道管理、消防経費、祭礼経費等の「町入用(ちょうにゅうりょう)」は、地主が間口割で負担し、運営を行うというシステムでした。
江戸の「町」は、図2で見るように間口60間(両側で間口120間)、奥行20間の街区が道路(往還)を挟む両側町が基本でした。京都や大阪などでは一筆の宅地を1人の地主が店、奥、箱庭、離れ等に使いますが、江戸の町屋敷では、間口5〜6間の短冊状の宅地を、表店と、路地を入ると一面につくられた九尺二間(六畳程)の棟割長屋の裏店が並び、宅地半ばに共同の井戸や便所、芥溜(ごみため)がつくられていました。江戸の町は、稼ぐための場所として低層高密度な土地利用が行われていたのです。(図3、図4、図5)

図2/江戸初期の中央通り両側町

図3/嘉永年間頃の神田商職の街構成(作図協力・深澤晃平)

図4/神田三河町の町屋敷図 (『江戸住宅事情』東京都)

図5/斎藤市左衛門(月岑)所蔵の沽券図(学習院大学図書館蔵)
武家地は幕府から一時的に拝領しているだけでしたが、町地は沽券地(こけんち)として町人の個人所有地でした。現在の公図にあたる「沽券図(こけんず)」(図6)には、町屋敷の区画割り、土地の寸法や形状、売買金額、地主や家守の名前も書きこんであり、土地の売買や譲渡があると「水帳(御図帳(みずちょう)」(図7)に記載し、支配名主が保管していました。

図6/町屋敷の入口、表店の横に木戸があり裏長屋に続いている(国会図書館蔵)
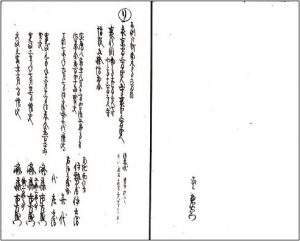
図7/斎藤市左衛門所蔵の水帳写(神宮文庫所蔵)
新しく地主になる、すなわち土地を所有するには、その町の地主全員の同意が必要で、新たな所有者はお披露目により町の構成員となることができました。町中で犯罪が起これば全地主が連座して責任を負います。たとえ大金を積まれても、町に素性の知れぬ者が入らないように、全員同意を基本とする町政が成り立つようになっていたのでした。「コケンにかかわる」とは、ここから生まれた言葉です。
「町」は、治安維持のために両側町の両端に木戸が設置されており、夜間は門を閉めていました。門際には木戸門の開閉の管理のために木戸番屋が置かれ、また地主自身が公用・町用を勤めるための「自身番屋」があり、五人組にて月番で詰めていました。そこは、町奉行所からのお触れを伝えたり、火消道具や捕物の道具を備えた現在の警察、消防、区役所などの出張所機能を兼ねた場所になっていました。(図8、図9)

図8/自身番屋〈左〉、木戸〈中央〉、木戸番屋〈右〉(国会図書館蔵)

図9/自身番屋に詰め る家守(国会図書館蔵)
地主の負担する「町入用」の原資は、店子の地代・店賃でした。そのため地主は、店賃を確実に納めてくれる店子を入れ、育てることが必要であり、収益を上げるにはより高い地代・店賃がとれるような町を目指す必要がありました。江戸の町は運命共同体のようでいて、都市型の協同組合のようでした。

図10/古い公共構成と家守の人間関係(作 図協力・深澤晃平)
地主が“地域に対して無限責任を負う”システムでは、地主自身がタウンマネジメントの役割も担う半官半民の町役人として位置づけられており、町奉行所へ訴訟できる市民権を持っていました。江戸の町は不在地主が多く、代理人として家守を地面に張り付けざるを得なかったのです。狭い意味での町人とは、居付地主たる「家持」と地主の代理人たる家守を指していました。
江戸は身分により住む場所や所管となる役所が違いました。町人の住む町地は町奉行が管轄しており、南北の町奉行所は、月番交代制で訴訟事を引き受け、配下には与力が 50人、その下には同心が200~300人いました。このわずかな人数で町人地を管轄するのは困難なので、「町役人(ちょうやくにん)」と呼ばれる3人の町年寄と、250~300人の名主(平均して6~7町を支配)を置きました。さらに、幕末期の江戸には家守が2万人余りいたのです。町人人口が50万人だとすれば、実に25人に1人が家守だったことになります。
家守は店子の日常的な面倒から奉行所への店子の訴訟等、地主に代わり町役をこなしていました。そのため宅地内の差配を行い、地代・店賃を集め、地主から「年給二十両」、五節句の際の節句銭や引っ越してくる際の樽代等の「余得十両」、長屋の便所の糞尿を農家に売ることで「糞代十両、おおむねおよそ三、四十両」の収入を得ていました※3。(図10)
3.東京・現在の公共によるまちづくり
明治に入り幕府が解体すると、沽券地であった町人地の宅地を除き、武家地は全て上地となりました。大名といっても土地を所有していたわけではなく、幕府から地上権を認められ屋敷を構えていただけでした。しかし、旧武家地は広すぎてそのままでは家業を前提する地借店借としては使えません。従って明治のまちづくりは、宅地内を細分化する道路づくりとセットで進行します。

図11/明治6年作成の多町二丁目辺の沽券図(東京都公文書館蔵)
明治2年10月、江戸の公共を支えた「町奉行所―町年寄―名主―家持・家守」によるシステムは解体され、道路や上下水道の管理、警察、消防などは東京府の仕事となり、家守は担っていた役割から公的な仕事がなくなり、「家守・家主」の名称は東京府により「地面差配人」へ変更されました。
さらに、明治6年、全国レベルで地租改正が行われます。近世の租税の形態は年貢として農地から物納を基本とすることから、すべての土地に評価額を定め、一定の率で地租を取る制度に変わりました。町人地は沽券図により取引額が明確でしたが、武家地は取引の対象でなかったため、近隣の取引額を参考にして定められました。これにより、東京の宅地全てに「地番」が付けられ、「東京の町」は個々の宅地を束ねるための単なる名称となり、武家地にも町名が付けられました。地租は中央政府が集め、地域の行政需要に対し分配される税制が始まりました。これにより、「江戸の町」は地域自治の単位でなくなると共に、「家持・家守」はタウンマネジメントの主体から外されました。(図11)

図12/明治33年頃の中央通り、限・須田町1-24辺(東京名所図会・著者蔵)
明治29年には民法が整備され、不動産の法的位置付けが明確になり、不動産の売買や仲介を行う業務が可能となりました。一方で江戸から家守業を担っていた人の減少にともない不動産仲介業が成立していきます。明治33年頃の神田中央通り(現・神田須田町一丁目24番地辺)を撮影した写真(図12)に、貸家周旋業・便利屋と呼ばれた現在の不動産仲介業の看板が見えます。看板には「(地)所建物売買貸借取扱」と書かれています。東京神田の老舗である「藤川不動産」や「光正不動産」もこの頃の創業のようで、非常に興味深い写真です。
地主や家守によるタウンマネジメントの主体が消え、伝染病等が発生した場合に地域全体で対応せざるをえない新たな地域主体として、地域住民を中心とした「町会」が生まれます。町会は、東京府が拾いきれなかった「伝達機能」や「祭礼」執行の役割を担うようになりました。
言い換えれば、近代化により「古い公共」を支えた家守の末裔が、「区役所」と「町会」、それに「不動産業」となったわけです。しかし、地域の安全を支える主体は区役所や町会に残ったものの、地主が連携して地域価値を高め、高い店賃のとれる地域を目指すというタウンマネジメントの直接的な担い手は消えてしまいました。
4.「新しい公共」としての現代版家守

図13/三鷹SOHOパイロット オフィスの見取り図
バブル期は東京都心の事務所面積が足りなくなるといわれ、米軍の空襲で焼けなかった都心エリアでは強引な再開発が進みました。戦後は持ち家政策がとられ、宅地が細分化された職住一体の木造建築物で構成されていましたが、バブル期は地上げ屋により虫食い状態のようになり、神田地区も空き地や空きビルが残るエリアとなってしまいました。
塩漬け状態となった地域でのまちづくりをどう展開するかという課題の前に、都市計画法や建築基準法は建設時に使うもので、今ある施設を活用するにはほとんど役だちません。また、産業振興といっても、小売業振興策はあってもまちの界隈を特徴づける卸問屋への支援策はなく、まして中小ビル管理業への支援策は全くありませんでした。
一方、バブル後は、小規模な在宅による「家業」ならぬ「個人業」が期待され、「テレワーク」というITを使いこなすようなワークスタイルも語られるようになりました。このような時代の変化の中で1998年12月に、㈱まちづくり三鷹による「SOHOのパイロットオフィス」(図13)が開設され、見学する機会にめぐまれました。ワンフロアを区割りしてSOHO事業者を集め、そこには井戸端ならぬコピー機端があり、受付には家守のような役割の人がいます。これを見て、まさにこれは江戸宅地利用と同じだと感じました。
これからの不動産業は従来型の仲介業ではなく、テナントの力量を見抜き、育成し、地域の付加価値を高められる新しい「現代版家守」としての職能が必要です。しかしながら、大手不動産業者は組織で仕事をしているため動けませんし、このようなことに取り組もうとしても、中小ビルには残念ながら支える組織もなければ「現代版家守」の担い手もいません。
そこで、“バブル後の神田の空きビルを活用するには、不動産経営の経験のないオーナー(地主)の代わりに、代理人としての家守をおいて、複数の中小ビルを束ね運営すればいいのではないか。そして、地域内の家守が連携し、個々のビルのみならず、地域全体の価値を高めるエリアマネジメントを進めればいいのでないか”と考えたのです。

図14/現代版家守の再生

図15/「SOHOまちづくり」事業のイメージ
一方行政は、「現代版家守」たる者を評価し、彼らが活躍できる場を用意することが必要で、会議室などの収益を上げるのが難しい共有施設や固定資産税のかからない公共所有施設を活用すれば、江戸のまちづくりのようなことができるのではないかと構想しました。
ちょうど秋葉原に千代田区に寄付された戦前のビルがあったので、これを自らリノベーションし、“地域活性化につながるSOHO事業者を育成する施設として活用できる事業人材を公募する”という実験事業を行うことにしました。10年間の定期建物賃貸借契約にして、区の施設であることから固定資産税相当分を助成する方法で賃料を安くして、財団が連携してまちづくりを推進することにしました。その結果、2001年12月に誕生したのが「リナックスカフェ」です。そして、この事業の実績と課題を踏まえて2003年3月に前出の提言書を出しました。委員会では、ビル所有者と家守の事業展開にサブリースではない共同事業者としての役割の整理、担保を持たない家守事業者への支援策、民間施設での運用可能性の検討等が行われ、2003年11月には、日本政策投資銀行による家守事業を支援する「SOHOコンバージョン支援センター」が開設されました。
この提言書をもとに、構想を実際に試算した民間施設が「REN-BASE UK01」として誕生し、さらに発展して「セントラルイースト東京」というアーティストを集積するプロジェクトや秋葉原で現在進行中の「3331事業」に至っています。また、提言書の内容を具体化すべく、区の施設である「中小企業センター」を普通財産にし、地域の中核施設としてSOHO用途にコンバージョンして活用する家守事業者を公募しました。そこから2004年「ちよだプラットフォームスクウェア」が誕生し、2006年からは財団は「家守塾」を開き、「現代版家守」の育成を始めました。これは、現在全国展開されている「リノベーションスクール」の先駆けとなったものでした。
5.まちづくりの目的「町々安全・商職繁昌」

図16/平河天満宮の銅鳥居
図16は、千代田区の半蔵門近くに鎮座する平河天満宮の銅鳥居です。天保15年に建設され区の文化財となっています。地域から寄進された鳥居の右柱には、「町々安全・商職繁昌」と記されています。それは、生活している者の場としてエリアが「安全」で、そこに暮らす町人=商人・職人が「繁昌」することを祈願したもので、今も昔も変わらない鎮守の意味を持ち、まちづくりの目的ともいえるものです。
残念ながら現在は、地域の安全と繁栄の両方を担うべき組織が見当たりません。中小ビルオーナーはそれぞれが競争相手でもあり、個々の敷地の枠を超えることは難しいようです。しかしながら、江戸からの歴史を見ると、エリアマネジメントの担い手は、住民でもなく、テナントでもなく、地域の不動産所有者だと私は考えています。
不動産賃貸業・管理業は、江戸・東京を通して、都市にとって最も重要な都市型産業です。個々のオーナーが、不動産仲介業を通してテナントに向き合うのではなく、地域としてテナントに向き合える仕掛けが、いま再び求められています。自らの資産価値の向上は、地域価値の向上を抜きにして成立しません。地域に無限責任を負うべき中小ビルオーナーが連携して「地域産業の活性化と地域コミュニティの再生」による地域価値の向上を図るべく、オーナーの代理人たる「現代版家守」が神田に再登場することを願ってやみません。
本稿で紹介した「ちよだプラットフォームスクウェア」等の家守実験事業は、公共施設という固定資産税のかからない施設を逆手にとって成立しました。今後の家守事業を支える原資は、都市計画法などで、個々のオーナーが地域活性化に貢献する施設をつくると容積が割増しとなり、整備ができるというものではなく、逆に、エリアマネジメントの主体が、地域活性化に貢献する公共的施設を既存の民間ビル内に設けた場合、そのビルの固定資産税の一部を地域のエリアマネジメント経費に使えるという、固定資産税を財源とする新しいシステムが必要ではないかと考えています。つまり、地域が努力し路線評価額を上げることで直接地域に還元されるシステムが、今求められているのだと思います。地域内の資産活用が、競争ではなく共有施設として位置づけられて適切に資産評価がなされていく「新しい公共」による、大都市内での地域競争を前提としたまちづくりの仕掛けが必要なのではないかと考えています。
※1 現在「まちみらい千代田」
※2 https://www.mm-chiyoda.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/sohoteigen.pdf
※3 『近世風俗史一』喜多川守貞著(岩波文庫)
 小藤田正夫 氏
小藤田正夫 氏
1952年千葉県生まれ。大学卒業後、1975年、千代田区役所に勤める。千代田まちづくりサポート事業、現代版家守事業などの創設展開にかかわる。また、神田地域の人たちと『江戸名所図会』で有名な斎藤月岑の研究会を設立。2004年、生誕200年を記念して居宅跡(神田司町二丁目)に顕彰碑を建立。定年退職後は、NPO神田学会理事、東都町造史研究所理事など、都心町造の調査研究を行っている。共著書『コンバージョン、SOHOによる地域再生』『神田まちなみ沿革図集』『外濠』